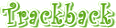常に読むものが無いと苦しい活字依存症。
[PR]
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
てなわけで(バレンタイン企画ふーふ編)
・・・なんなのかしらこの遠足前日に興奮しすぎて眠れない小学生のような身体は。
そんなわけで(いや、話がつながってないから)、ブログ開設以来初!のバレンタインですので、なにか上げたいじゃないか企画第1弾。です。
頂いた本を読んではむはーーーーーっと興奮しながら打ってるので、なんか話が通ってるか心配ですが、まだ次が控えてるからとりあえずアップ!してしまいますです。相変わらず勢い任せだ・・・
そういえば、アフターの場で、「一体自分の書いてるSDは、いつなんだか自分でも分かりまへん」てな話をしてたんですが、家に帰って改めて考えても分かりまへんね。一体全体いつなんだねこれは。そんなものを今日も書いてますです、すみません・・・
弟兄呪、ネタを毎日考えております!
今しばらくお待ちくださいませ~~(平伏)
ディーンは憂鬱だった。
もうすぐバレンタインデーだ。
サムがまた「夫」になるかもしれない。
前から薄々思っていたが、どうもサムはイベント好きだったらしい。
クリスマスにも「夫」は出てきた。新年のカウントダウンにも、ディーンの誕生日にもだ。
ずっと兄弟に対しては『そんなこと興味ない』てな顔していたくせに、実は一人の男としてのサムは『イベント&くさい演出大好き男』だったのだ。バレンタインだからあれだ。外で飯食ってるときに花束持ち込んだりとかしやがったらどうしよう。頼むから他人の目があるところではやめて欲しい。
もちろん何事もなく過ぎて、こんな心配不要に終わる可能性だってある。
この世に生を受けて三十年ちょっと。
こんなバカバカしい心配をするバレンタインデーは初めてだ。
兄弟だったら知らずに済んだ弟の一面を知ってしまったディーンは、今とても苦悩している。
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
だが当日。
「ディーン、なにか見つかった?」
「・・・いや、類似の事件も無いし、被害者に目立った不審点もないな」
「切り上げて他の町に移動する?」
「そうだな・・・」
「あ、待って。被害者の同僚でまだ話を聞いてない人がいるから、一応確認してみた方がいいかも」
ラップトップを睨んでいるサムは、とっくに昼を過ぎた今も普通に「弟」だった。
男兄弟二人のハンター稼業で、バレンタインの「バ」の字もあるわけがない。
心配しすぎた俺がアホだった。めでたい。
「そしたら」
聞き取りの前に飯でも食いに行くか、と言い掛けて口を噤む。
ほどほどに人の多い街中に出れば、バレンタインの雰囲気は強い。
もしかしたらサムは今日がバレンタインデーであることを忘れているかもしれないのに、外に出て思い出されたら危ないかもしれない。
「何となく気になるから、今日一杯だけ調査は続けよう。俺は午後聞き取りに行ってくるから、お前は何か過去の記事とかないか見てみてくれ」
「いいけど、FBIで行くなら二人一組が基本だろ」
「いや、友人でも名乗るから一人でいいさ。分業だ。効率よく行こうぜ」
「ま、いいけど」
サムは不審そうだが別にいい。当日さえ越せば、こんな警戒は別にしない。
イベントで寒いことをしなければ、別にサムがハグ魔になろうがキス魔だろうがそこはまあいいのだ(こういうことを言うとまたボビー辺りは微妙な顔をする)。
「腹減ったな。ピザでも頼もうぜ」
と言った瞬間に部屋のベルが鳴らされ、二人は顔を見合わせた。
「・・・・お前、ネットから注文とかしてたのか」
「まさか。ディーンじゃあるまいし」
軽口を叩きながら互いに銃を手に取り、ディーンはそっと外の様子を伺う。そして、一瞬目を丸くした後、微かにため息をついてドアをあけた。
「ディーン・ウィンチェスターさん?」
立っていたのは制服を着た配達員だ。手には巨大な赤い薔薇の花束があった。
「Sei sempre nei
miei pensieri
e nel mio cuore.」
シンプルなカードにタイプされたメッセージは英語ではない。
部屋には微妙な沈黙が落ちている。
「・・・なんだこりゃ?」
とディーンが呟くと、
「イギリス風だね」
とサムが答えた。
「へえ」
「向こうだと、プレゼントに匿名のカードを添えて想いを伝える習慣らしいよ」
「ふーん」
よく知ってるな、というか、明らかに送り主お前だからな。
そうか、お前イギリス流にやってみたかったのか。
せっかくの試みを受けるのが実の兄貴だっていうのがあまりにも不憫で泣けてきそうだ。
「贈り主に心辺りあるのディーン」
何となく憮然とした声でサムが言う。
「そりゃあな。こんだけいい男だと有りすぎるほどあるさ」
「いつの間にこんなに熱烈な男のファンができたのさ」
「男?俺に一目ぼれしたレディーかもしれないじゃねえか」
言ったせりふはさくっと無視される。
「それ、イタリア語だ。『あなたはいつも私の想いの中に、そして心の中にいます』って意味」
「へー」
くさい。しかもイタリア語。読めん。
色々な意味でサムらしいなあと思ってしまい、ディーンはちょっと笑った。
「無用心なんじゃないの」
不機嫌なサムの声で我に返る。
「何がだよ」
「他人に泊まってるモーテル教えるなんてさ。しかも本名で」
「心配ねえよ」
お前だし。
「信用できるの?」
「まあ、まず大丈夫だ」
お前だし。
「大体、このメッセージだって変だよ。これは、・・・告白っていうより、ディーンを恋人とでも思い込んでるような感じだ」
「まあ、ほっとけよ。害は無い」
お前が兄ちゃんと夫婦だと思い込んでるせいだし。
「こいつ変だよ?大丈夫なのかディーン」
「大丈夫だって」
お前なんだから。
「・・・僕がディーンの立場だったら、そんなに簡単に信用しない。その花とカードも、念のために処分した方がいいと思うけど」
「しねーよ!心配いらねーっての」
「誰?そいつ。イギリス人?」
なんだ、このメンドクサイ事態は。
夫と思い込んでサムがやった行動を、正常な状態のサムが「変だ」と言う。何で俺がそれを宥めなきゃならんのか。
俺、今日はハラペーニョ乗せたピザ食いたいんだけどな。
ディーンは次第にぐうぐう鳴り出した腹を感じながら、調査そっちのけでイギリス出自の知り合いの名を列挙しだしたサムをもの悲しく見つめた。
夜。
風呂を済ませたディーンがソファでテレビを見ていると、隣に座ったサムがそっと髪を撫でてきた。
「髪、まだ濡れてるよ」
(あ、変わったなこいつ)
思った瞬間、思わず口が滑る。
「・・・遅えよ」
結局あれから一応調査は続けたものの、ディーンが花束を捨てず、相手の名前も教えなかったのでサムは午後中機嫌が悪かったのだ。
あり得ないことだが贈った当人になってくれて、ホッとしてしまった。
しまった、と一瞬ぎくりとするが、「夫モード」のサムはいつもながらてきとーに状況を解釈してくれた。
「ごめん、待っててくれたの?」
言うと立ち上がってフリッジからビールを2本取ってくる。
はい、と栓を抜いて手渡され、大人しく受け取ってカチリと瓶を合わせた。
「男に薔薇の花束とか、ありえなくねえか?」
一口飲んだ後、ディーンはやっと午後中我慢していた言葉を口にした。
「捨てられなくてよかったよ」
サムがくすくすと幸せそうに笑う。
「イタリア語なんかで書かれてもよめねーっての」
「ごめん。なかなかぴったり来る詩がなくてさ」
「・・・詩なのかあれ・・・」
げっそりとディーンがソファーにもたれると、サムはまた笑う。
「外でディナーしてもいいかと思ったけど、今日はどこも混むしね。ディーンがカップルだらけの店で食事は恥ずかしがるかなと思ってイギリス風にしてみたんだ」
「へー・・・・」
お気遣いいただいてどうもと言うべきか。どちらにしてもぐったりしたことに変わりは無いように思う。
やっと言いたいことを言ったせいか、急に眠気が回ってきて、ディーンはソファにもたれたまま目を閉じた。
「眠いの?」
「んー」
肩に回った手にゆっくりと引き寄せられて、Tシャツの肩に頬が触れるのを感じる。大きな手が何度も髪を撫でた。
「・・・濡れるぞ」
まだ濡れてるって自分で言ったんだろ。モゴモゴと口にすると頬と腕の触れている身体が動く。サムはまた笑っているらしい。ディーンは身体の力がますます抜けるのを感じる。夫でも弟でも、サムが笑うとディーンはほっとして幸せな気分になる。
頭にタオルの感触が被さってくる。サムが風呂上りに使っていたものだろう。サムの匂いがした。
ゴシゴシと髪を拭かれると、サムの肩から頭がずれる。重力に従ってずるずると下に落ちた。頬の下に感じる硬い筋肉と弟の匂い。ああ、なんだこりゃ膝枕になってんのか。
「寝てていいよ。運んであげる」
頭の上でサムの声がする。少し掠れた、その声にまずいものを感じて、ディーンは最後の意志力で釘をさした。
「・・・なんもするんじゃねえぞ・・・」
今日の俺はダメだ。何かあったら絶対流される。しかも眠い。
ヤバイと思いつつ、ハンターとしての警戒警報はサム相手には発動してくれない。ディーンはそのまま眠気に飲まれていった。
そして朝。
サムは「夫」のままだった。
「・・・・・不満だったわけだな・・・」
サムはきちんとディーンの意志を尊重した。いやまあ、男としてはわからなくもない。しかし、ディーンとしてもダメなモンはダメなのだ。
「ディーン?どうしたの」
車に荷物を積みこんだサムが振り返る。ちょっと手を伸ばしてディーンの口の端を触り、
「パン屑ついてる」
と笑った。
夫のサムを満足させて早く弟に戻すためには、モーテルに置いていくつもりだった花束を、インパラに積まないといけないのかもしれない。
(サムが弟に戻ったら、またうるさいだろうな)
ディーンは思いながらチェックアウトのためにフロントに向かった。
おわり
夫の出番が少なかった・・・

 管理画面
管理画面